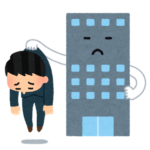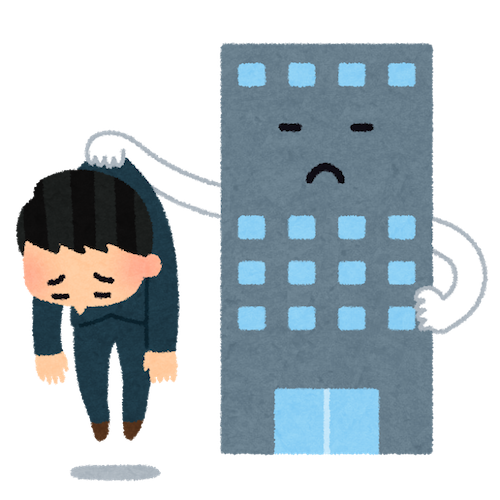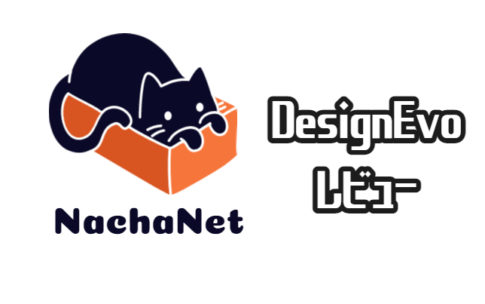通勤列車も冷房が効いてくる季節ですね。『なー』です。
一つ前の記事で、僕が会社と戦うことになった経緯について書きました。
僕はこれでADR法(あっせん)という制度を使うこととなります。
今回は、実際に会社との争いで活用したADR法(あっせん)について説明します!
ADR法(あっせん)とは
ADR法(あっせん)とは、労働者と会社とのトラブルが発生したとき、双方の間に社労士や弁護士が入って互いに話し合うことで和解を目指す制度です。
この制度が便利な点として
・証拠の必要性が低め(もちろんある方が良い)
・裁判ではないので弁護士探しなどが不要
・相手と顔を合わせなくて済む
といった特徴があります。僕は無料という言葉につられ、即決しました。
ただし労働審判と違って強制力はありません。
なので会社が呼び出しに応じなければ交渉決裂。その時点で手続きは終了となります。
全国規模の大きい会社であれば応じてくれると思いますが、中小企業などワンマン経営者であれば「知らねーよ!」と一蹴される可能性の方が高いです。
あと、委員会の人は聞き取り役と、双方の主張を相手に伝えるだけの役割なので、「会社は解雇を無効としなさい」といった命令などはできません。

こんな感じに双方の間に入って話を聞いてくれるだけです。交渉が決裂したらその時は労働審判ということになります。
…が、労働審判は時間がかかるので、できれば交渉決裂は避けたいと思う人もいるかもしれません。
でも、これは相手も同様です。
そのため、精神的にも立場的にも有利になるには
そっちがナメた態度とるなら労働審判までやってもいいんだぞ!
という心構えでいることが、交渉を進める上でとても大切です。
僕の場合、ブログをやってるのでネタになるのであれば労働審判までやってもいいかなと思って挑みました。
2度目の労働審判というのもかなりレアケースでしょうし。我ながら変態である。
社労士さんに連絡をとるには
全国の地域ごとに「社労士会」と呼ばれる団体があります。
Googleで「北海道 社労士会」のように自分の住んでいる都道府県名をいれて検索するとすぐ出てくると思います。
たとえば北海道だとこんな感じ。

こちらの夕方から開設している電話窓口まで相談したときに「ADR法」という制度があることと、内容について説明を受けました。
電話口の社労士さんは労働審判の大変さもわかっているようで、ADR法についての説明を受ける前に、僕が労働審判も視野に入れていることを話すと、
「弁護士費用もかかりますし、意外と時間かかりますから大変ですよ?」
とのことでした。
ぼかぁもう労働審判の経験者なんですけどね…ふへへw
電話でADR申し込みと資料作成を行う約束をとりつけ、1週間後に札幌の紛争解決センターへ向かいました。
建物、けっこう古いです。入り口も目立たないので、人によっては見つけられずに迷ってしまいそう。


事前に今回の手続きをスムーズに進めるため、以下の内容をまとめた書類を持って行きました。
・派遣会社名
・本社の所在地と電話番号
・札幌支社の住所と電話番号
・派遣会社の代表者
・派遣先の名称
・僕についた担当者
・口頭で伝えられた雇止め理由
(上司にタバコ臭いと指摘した、顔が怖い…など)
・1年以上契約更新が続いているため無期雇用と変わらないこと
・元の職場への復帰、もしくは給与3ヶ月分の和解金どちらかを希望すること
・いずれも受け入れない場合は労働審判を起こすこと
など、雇止めの理由と雇止めを無効とする根拠、解決しない場合の内容を書きました。
これに加えて、発行してもらった雇止理由証明書のコピーを証拠として提出します。
雇止めの理由(タバコ臭いと上司に指摘した、顔が怖いなど)を見たときの社労士さん曰く
「こんな理由で…追い出されたんですね…雇止理由証明書に理由が何も書いてないですし…」
とのこと。争う余地は十分にありそうです。持っていた資料をもとに書類を作成します。
要点をまとめた時点でだいぶまとまってたので、持ち歩いていたMacBookで社労士さん監修のもと語調を変える程度でサクッと申立書を作成。
さて、できあがった書類を誰に出すか…
社労士さんは、
「支社宛てに送っても握りつぶされそうな気がしますし、それなら本社まで送るのがベストでしょう!」
と言っていました。
派遣会社の僕の担当者は、雇止理由証明書を渡すときに
「何かありましたら僕に直接連絡してください」
と、上司などに隠して大事(おおごと)にしたくないという雰囲気を出しながら言ってました。
でもこいつ、僕が何を言おうと「いや〜先方がこう言ってますから…」とだけ毎回のように返してきたクズです。
僕の言い分を一切聞こうとしなかったこのクソ無能を経由していい結果になる想像ができません
なので、社労士さんの言うとおり、本社の社長室まで送りつけました。
僕の担当、大目玉食らうんだろうなぁと考えるとこの時点で勝った気分です。
送付含む手続きはおおよそ2時間ぐらいかかり、1週間後、社労士会から
「あっせんを受け付けましたから会社からの回答を待ってください」
と書かれた封筒が届きました。
…
さらに1週間後に社労士会から電話がかかってきて
「相手の会社があっせんの場に応じる回答がありました。開催日を追って知らせます。」
と連絡がありました。
さらに2週間後、無職には関係ないゴールデンウィークが終わったころに簡易書留が届き、あっせんの開催が正式に決まったとの内容が通知されました。

社長自ら来るのか?
気になりますが、あっせんの開始日を待ちます。
次の記事で、実際のあっせんの流れがどんな感じか詳しくまとめています。