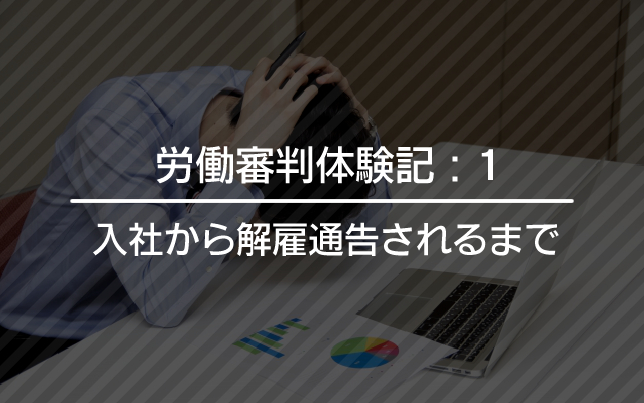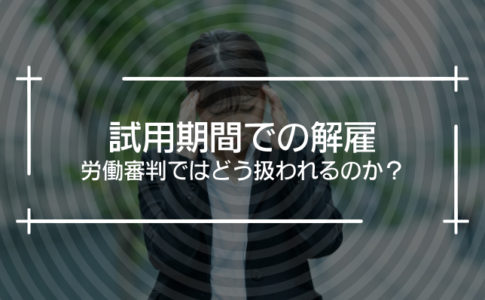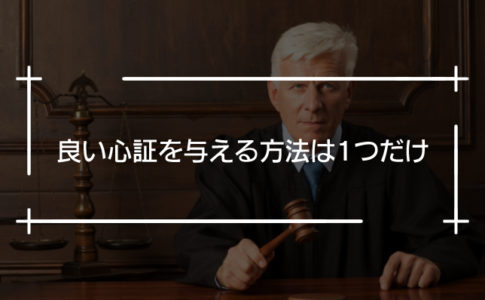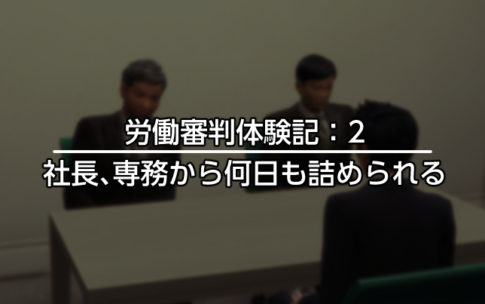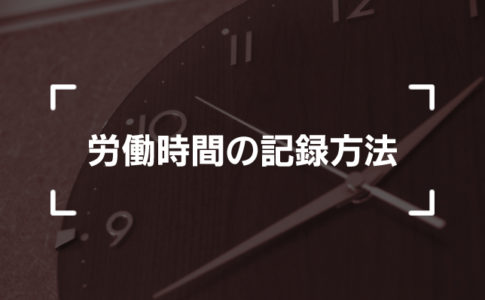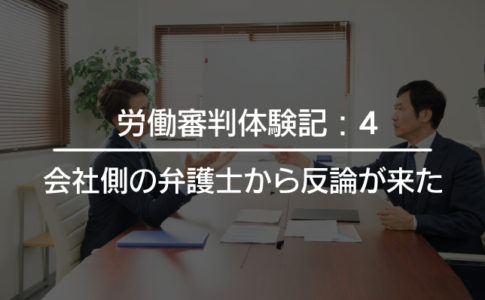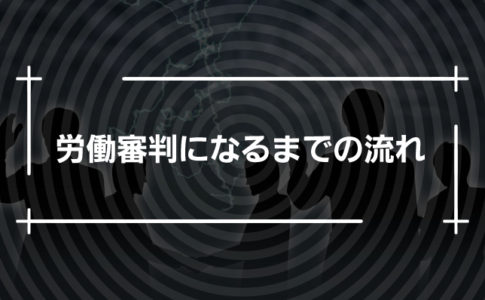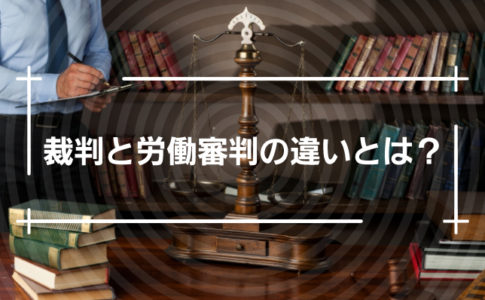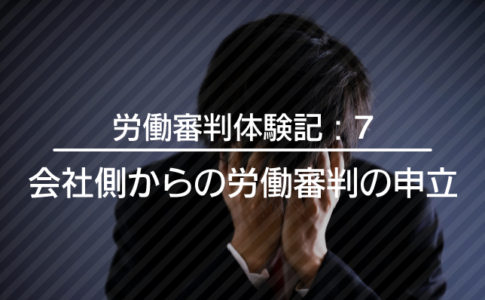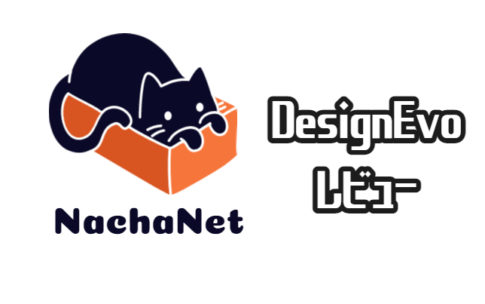ハロー、おかえり同志。
この記事から労働審判についての体験を書いています。全部1つの記事に書いたら超長くなるので、分けてまとめています。
書いてしまうと(記載内容が事実であっても)名誉毀損にあたる可能性があるので、残念ですが社名や個人名は伏せています。
すべての内容は下記記事から参照できます。
入社から3ヶ月目まで
2015年、僕はソフトウェア開発事業を行う社員50人ほどの会社に入社しました。
トライアル雇用なので実務経験はありませんでしたが、情報系の大学を出ていたので研修でつまづくことなく業務をこなしていました。
これは同じチームにプログラムについてとても詳しく、わからないことがあったら気軽に聞ける上司がいたためです。
この上司は僕にとっては師匠ともいえる人で、僕の解雇に最後まで反対してくれました。
今でもプログラムを書くときはこの人の教えてくれたことが根底にあります。
……このときは素敵な上司もいたため、仕事も楽める余裕を持ってやっていました。
勤務態度も能力にも問題はないと判断され、トライアル雇用期間を終えて正社員として正式に採用されました。
プロジェクト移動1ヶ月で解雇決定
ところが入社後4ヶ月目、別のプロジェクトに移動することになり状況が大きく変わりました。
このプロジェクトチームは、違う上司と僕の2人体制でした。
やることが完全に変わったので、やるべきことや不明点は当然聞いて作業しようとするも、返答の内容というのが
「俺プログラムわからないから俺に聞かないで自分で調べて」
「Amazonのタイムセール見て忙しいから自分でやるべきことを探して」
と言った具合で、一緒に仕事して本当に大丈夫なんだろうかと、かなり不安でした。
別のプロジェクトに移動した時点で、何を目的にしたプログラムを書けばいいのかという基本的な部分すら知らされない有様でした。
入ったばかりの僕一人で作業は進まず悪戦苦闘…そんな僕とは対象的に部長は扇子で顔を扇ぎふんぞり返って釣りの道具をAmazonで探しているという有様です。
そのような状況が1ヶ月近く続き、遅くまで残業しても成果をあげられず…
8月の終わり頃、能力不足によりプロジェクト移動から1ヶ月足らずで解雇が決定しました。
「どうか考え直してください」「至らない点があれば直します」と言っても「もう決まったことだから」と一切聞き入れてくれず、早く辞めて転職活動をしろと自主退職を促されました。
会社都合の解雇だと解雇予告手当の負担や助成金の打ち切りなど不都合なことが多いので、労働者の自主退職の方が都合が良いからです。
当然ですがクビだから転職活動しろと唐突に言われても、納得して受け入れることなんてできるわけがありません。
解雇は受け入れないということを会議室に数時間詰められて退職勧告を受け続けました。
「自分が戦力にならないってわかってる?」
「なんで自分から辞めなかったの?頭おかしいの?」
など、部長や役員から毎日数時間言われ放題でした。
退職勧告を聞いている間、目眩で視界が暗くなっていき、泣きこそしなかったものの解放された後は悔しい思いでいっぱいでした。
その日から会社を行き来する列車や、トイレの個室に行ったときのわずかな時間にもスマホを開いて「解雇 無効」といった言葉をGoogleで検索し続けました。
なんとか解雇を無効にできないか、場合によっては労働基準監督署に駆け込めば助けてくれるかも…と藁にもすがる思いです。
そうしてひたすら調べているうちに労働審判を知りました。
弁護士に依頼したり、裁判所に出向いたり手間がかかります…が、クビを言い渡された以上在籍期間も限られて、ためらっている暇はありません。
なにより調べている間に退職勧告で詰められてる間に言われたことが頭に渦巻いていて、悔しさがどんどん増してきました。
手続きが面倒だとかを考えるよりも、
仕返しがしたい
この負の感情が大きな原動力になりました。
会社と闘うことを決意
休みを挟んで3日間「不当解雇」について詳しく事例や手続きについて調べて、労働審判が今の自分にとって活用すべき最高の制度であることがわかりました。
解雇無効にするにしろ、最終手段として労働審判するにしろ弁護士に依頼する必要があります。
この時の僕には弁護士の知り合いがいなかったので、弁護士ドットコムから弁護士を探しました。

「労働問題」というカテゴリがあったので地域を「北海道」で検索するとたくさん弁護士が出てきます。
僕は下の条件に該当する人を探しました。
・若手で労働問題について詳しい人
・通いやすい場所に事務所がある
・初回の相談料が無料
若手にしたのは労働審判という制度自体が新しいため、法科大学院で最近の制度を勉強した若い人が詳しいんじゃないかという考えからです。
とはいえ、時間が本当になかったので評判などを調べる間もなく半ば直感で選びました。
当時のスマホのカレンダーを見返したのですが、内容が下の画像です。

前述の部長に詰められた退職勧告が7日で、正式な解雇通告は9月15日でした(間があったのは自主退職で出て行ってもらうための説得の期間)
労働審判を知った日が9日の帰りの列車で、そのため10~14日の4日間しか時間がありません。
土日を挟んでいるので大抵の法律事務所が休みなことを考慮すると、実質たった2日しか時間がありませんでした。
なのであまり考えている余裕はなく9月11日に電話で連絡し、予約を9月30日に取り付けました。
詳しい話は当日にすることになりましたが、電話口で
「会社からの書類にサインは絶対にしないでください!一度サインすると撤回できないので解雇に同意するといった書類にはサインしないでください!」
と、強い口調で厳命されました。
サインしないことがそこまで重要になるのか?とこの時点で思いましたが、非常に重要であることを後に知ることとなります。
解雇通告の時に社長から連日のように恫喝を受けることになるのですが、このアドバイスがあったことで一番やってはいけないことを避けることができました。
長くなりましたので次の記事に続きます。